��y������(469)�@����20�N11��11���`11��15��
|
���e��
|
�X�C���t
|
|
���e��
|
2008�N11��15��(�y)00��01��17�b
|
|
�^�C�g��
|
�q���̎ʐ^�ł��Q
|
|
|
�����́A�����ꖇ�ł��B
1977.6.24 ����w �P�Q�Q���B
�w�̕��i�Ƃ��ĎB�����̂ŁA�Ώۂ������������Ă��݂܂���B
|
��y������(470)�@����20�N11��15���`11��17��
|
���e��
|
�G��
|
|
���e��
|
2008�N11��15��(�y)11��09��11�b
|
|
�^�C�g��
|
�k�C���̉��䂩����
|
|
|
�X�C���t�l���B��ꂽ����w�̎ʐ^�A�ǂ����͋C�ł��ˁB���s���́A������Ԃ̔@��
��ۂ��܂����A�����̐��H�́A1985�N�ɔp�~���ꂽ������ł��ˁB����w���̂́A
���a���x�O�̊ՐÂȗ��n�ł����A�����ł킴�킴�x�����Č�ʂ̕ւ�}����
������́A�n�َx����i����ȂǁA�s�X�̋K�͂���r�I�傫���A��u�x���̌S���ł́A
�]�s���ɑ����A��m�����ƕ��Ԑl���K�͂�i���Ă��܂��B
�n�������̎�v��ʓ����ł��锟�ِ��E�����܍����́A�ǂ�������Y�p�o�R�ł����A
���ꐅ��Ƃ̊֘A�䂦���A���{�C�݂̕����Z�܂����s�X��i����`����������ۂł��B
����A���{�C�݂͑����ċ}�s�ł���ׁA������`���ւ̓S���́u�A�z�A���v�Ӓ�����
���܂�A�C�����]�������c���̂݁B����ƂāA�Ìy�C�������ꕔ��Ԃ��t�s����
���ꎖ�������A�،Ó��ȉ��́A�����l�����z�����ʂ������O���Ɠ��l�̑[�u��
�������\���������Ƒz�����܂��B
������u�A�z�A�����v�̎ʐ^�L�^�����߂�ƁA���s�S���̏��@�q�����U������܂��ˁB
���H���́A1968�N�̍��J���̎{�ݑ���Ŕp�~�ƂȂ�܂������A����ȑO����A������
�o�c���̉��A�^�c�𑱂��Ă����̂́A������̉��L�ɔ������{�C�ݏc�јH���̌`���A
���̍ۂ̍��S�ɂ�锃�������҂��Ă����ׂ������ł��B
���ꂪ���Ɏ��������Ƃ��Ă��A���݂܂ő������������ǂ����́A���Ȃ���^�I�ł��ˁB
������k�C���ł́A��Ӓ��H���ł���A�_�U�E�D���i�ꕔ�j�H�y�E�V�k�E�[���E����E
�N�ԁE�r�k�E�W�ÂƁA���S�����ŋ�H�������ł��Ă���A���S���܂߂�ƁA��������
�m�y�������сA�r���A���Ђ̓�H���Ɓu�����v���Ă����k�C����B�S���ȂǁA���[��
������������݂����ƌ����܂��B�k�̑�n�́A���Â����䂩�����ł��˂��c�c�c
|
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��15��(�y)11��57��38�b
|
|
�^�C�g��
|
���q�ݍs����Ԃł���!!
|
|
|
���������ז����Ă���܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł���܂��B
�@�X�C���t�l�̂��ʐ^�́A�u�f���炵���v�̈ꌾ�ł��B
�O�q���܂����悤�Ɂu�W�Q�S���v���u�P�Q�Q���v���A
�����̑z���o�̃��g���g���C���E�E�E�B
�ݍs�I�s���́A�{�P�b�Ƃ��Ă��āA�ʐ^�̗ނ͂قƂ�ǎB�e���Ă��܂���̂ŁA
���肪����������ł��B
�@�����̂悤�ɁA�u���q�ݍs�v�́u�Y���v���q�ׂ����Ă��������܂��B
��B�̊F�l���̘b��ɂł����Ē�����A�K�r�̌���ł���܂��B
�P�@���a�S�O�N��㔼�A�u�����{���v�͂��łɁu���c�v�܂œd������Ă��܂������A
���[�J����Ԃɂ́u���q�v���^�p����A
�m���[���ȍ~�́u���q�s�v�͑啔�����u�c�k�v�����̋q�Ԏd���āB
�u����t�v�ɍ݂��Ă�������̏f�����K�₵���A��ɁA
����ȁu�ݍs��ԁv�߂邱�Ƃ����X����܂����B
���w����������������ۂɎc���Ă���̂́A
���Z���̃J�b�v���������o�����q�Ԃɔ�я�����p�B
�j�̎q���ŏ��Ɏ肷��Ɏ�������Ė����̃f�b�L�ɏ�荞�݁A
�z�[���ɂ������̎q�̎�����������āE�E
�Ƃ����A�����u�f��v�̂悤�ȃ����V�[���B
���݂ł͂ƂĂ��z���ł��܂��A
����Ȓ��Ղ��������́u�����{���v�ɂ͂���܂����B
�Q�@���a�T�S�N�̉āA���k�ݍs�I�s�̐܁A
�u�H�c�v�n���́u�V�Ís�W�R�Q���v�ɏ�ԁB
�u�H�z�{���v�̏��S���y���݂܂����B
�����܂ł��Ȃ��ċ�́u���{�C�v���\�����\���܂������A
����ȏ�Ɉ�ۂɎc�镗�i�́u�ۊ��t�߂̓c�����i�v�B
�u�C�㓇�v���n�k�ŗ��ɂȂ������߂͓Ɠ��̕���������A
�m�ԉ������߂��������i��̊��ł������Ƃɑf���Ɋ������܂����B
����ɂ��Ă��A�u�H�z�{���v�ɏ���Ċ����邱�Ƃ�
�����Ɂu�P���v�Ɓu�����v���g�ݍ��킳��Ă���u���H�z�u�v�B
�I�݂ɏ㉺�̗�Ԃ��s���Ⴄ�_�C���͖{���Ɂu�������v�̈ꌾ�ł��B
�R�@���a�T�V�N�̔ӉāA�u�L���v����u���]�v�֔�����ۂ�
�u�|�����v�́u���������s�v�́u�T�O�n���b�h�g���C���d���āv�̋q�ԓݍs�ɏ�ԁB
�ߌ�R���߂��ɔ��Ԃ���u�L���v�ł͉��Z�r���̍��Z�����ǂ��Ə�荞�݁A
�T���Ґ��̎ԓ��͂��イ���イ�l�߁B
�������A�����R�n�ɕ��������Ă����ɂ�A
�P�l����Q�l���肵�Ďԓ��̊����������̂悤�ɂȂ�A
���Ɂu���㐼��v���o����͏����P�l�́u�݂����ԁv�ɁE�E�E�B
�I���́u���㗎���v�ŏ�芷�����u�����s�P�s�c�b�v�������P�l�̂݁B
�u�o�_���c�v�Ő����̏�q���������̈��g���́A
���ł��L���Ƃ��đN���Ɏc���Ă��܂��B
�@���X�Ǝ��炵�܂����B�܂��A���e�v���܂��B
�ȏ�u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
|
���e��
|
�}���l��38
|
|
���e��
|
2008�N11��15��(�y)14��14��54�b
|
|
�^�C�g��
|
513�� �ƒ���
|
|
|
ED76109�l
���k����B�������ɋA��ꂽ�l�ŗǂ������ł��B�i�����������H�H�j
511-512���͂܂�����513-514���͑��]�X��2�ӂł����獟��ɓ�����Ɣ�J
���ނ������ł��傤�B513���ő��]�����ԓx�X�o���ɗ��p���܂������A�����
�u���v�I��31��N�I��41�ɏ��ƁC�}�s501���̃n�l���i��聗��100-�����A����
�u�w�و�H���v���o�܂����B�Ă̒��Γ�����v�g����̒����ɉ��ށu�_���Ǒ��W���v��
����ƁA����PC�u�܂���v���эL���o��������Ɠ����l�Ȋ����Ń��[�O�i�[��
Siegfried Idyll��C���w���� �u�q��̒��v�̃����f�C�[�̕@�̂����R�Əo�ė���
�̂��o���Ă���܂��B�u�܂���v�ł͊C�ݐ��߂��ł��C�̏�ɖ����ӂ�ӂ핂���Ă�
�錩�����Ȃ̂����Ėk�C�������̖��̐[���ɋ����܂����B�V�x�m�Ŗڂ����炵�ċ���
�������ߋ����̌y�C���Ԃ����鎖���o���܂���ł����B
|
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��15��(�y)23��04��25�b
|
|
�^�C�g��
|
���������S�H�B
|
|
|
�@�{���Q�x�ڂ̓��e�Ŏ���v���܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł���܂��B
�@�}���l��38�l
�@���k�C�������̖��̐[���ɋ����܂���
�@�����̋��H�E�����ł́A�U�`�W������ԁu�C���v���Z�������ɓ�����܂��B
���Ԃł��A�u�X�[�p�[��������v���̓��C�g��t���đ��s���Ă��܂��B
�����A���̎������n�ւ����ł̐܂́A
�ו��ɂȂ邩������܂��A�u�E�C���h�u���[�J�[�v�������Q���������B
�^�Ăł��w�^������ō��C�����u�Q�O���v�ȉ��ł��̂ŁE�E�E�B
�@���ߋ����̌y�C����
�@�u�ߋ����c�O���v�̂��Ƃł��ˁB
�u�V���ЕҁE���{�S���n�}���P���v�ɂ��A�P�X�Q�V(���a�P�Q)�N�Ɂu���ᗡ�v�A
����ɂP�X�S�S(���a�P�X)�N�Ɂu�V�y�C�v�܂ŊJ�ʂ����u�V�U�Q�o�v�̌y�֓S���Ƃ���A
�����́u�n�v�ɂ�茡������Ă����悤�ł��B
���R�A�J��̂��߂̂��̂ł����A�ȈՋO�����J�ʂ���܂Ő�����̎����́u�D�^�v��
���͕G�܂Ŗv���Ă��܂����Ƃ�����b������A��l�̘J�ꂪ�E��܂��B
�@�G���l
�@���������Ǝm�y�������сA�r���A���Ђ̓�H���Ɓu�����v���Ă����k�C����B�S��
�@�����A�u�V�����v�̍��Z�ɂ��Ζ������o��������A
���Z�̋߂��ɐ̂́u�ԌɁv�Ղ����������Ƃ��L�����Ă��܂��B
�S�C�������k�̕ی�҂̕����A
���Z���������܂Ɉ�N�Ԃ����u����(��������)�v�Ƃ�����������
�ʊw�Ɏg�����̌����f�������Ƃ�����܂��B
�u�^�~�̓K���X�̌��Ԃ��犦�������������сA�炪�����Ő^���ԂɂȂ��Ă��܂����B�v
�Ɖ����������ɑz���o������Ă��������܂����B
�@�ȏ�A�u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
|
���e��
|
�}���l��38
|
|
���e��
|
2008�N11��16��(��)14��02��56�b
|
|
�^�C�g��
|
�k�C�����U�����B���O���H
|
|
|
ED76109�l
�Â����ԕ\�ɂ͂���Ȃ̂��o�Ă��܂��ˁB�ߋ��A�y���A�̓o�A�l���A�ʊC���i�ԈႢ
�����邩���m��܂��j----�B�o�������Ώ̂�DC�Ƃ���N�̃L�n02�݂����Ȓ���
�o������Ƃ��A�H�Ղ������̂ŏ��^�{�M�[�q�ԂƂ��]�]�]�X�W������ꉝ���ʼn��n��
���Ł]�]�ʊC�͍Ō�܂Ŕn�ԓS���������Ƃ��ł����ˁB������B�O���̃o�X�^�K�\
�Ƃ�����Č����������ł��B
���̂��̎�O���̌o���́u���їp�O���vBW��B-1�d�����R�ł������A������Ԃ�DL��
����ŏ��C�͉^���ݕ�����ł����B�k�C���̊ȈՋO�����F�X�Ȑ��������^����
��ڂ������ł��傤�B
���Ԑ��́u���Ձv�ŊȈՋO���̎Ԃ��ԑ����猩���܂������A��Ԉʒu�Ƃ������Ԃ�
�ʂ����Ȃ��܂����B
�����́u�k�C����B�S���v�ɂ͐����̒��Â�DC�ƃL�n22�݂����Ȏԑ̂�DC��������
�ł͖����ł����H�u���ԕ��v�͑��������̒��Âł��傤�B
|
|
���e��
|
�}�s�z�O
|
|
���e��
|
2008�N11��16��(��)22��13��56�b
|
|
�^�C�g��
|
�����{���S�Q�Q��
|
|
|
�������ݍs�̎ʐ^������܂����B���x���b��̏o�Ă���k�C���ł��B
�O���ɎO�H�ΒY�{�Ƃɏ���āA�D�y�ɖ߂��ĂP�S�n�u�܂���v�ŋ��H�ɂɓ���A
�܂�Ԃ����܂ŏ�Ԃ��Ă��܂��B
��������P�O���ԋ߂��������Ă��܂��ˁB
�����{���S�Q�Q���i���H�V�F�R�T�`���P�V�F�Q�P�j
�c�c�T�P�U�R�X�i���j
�}�j�@�T�O�Q�P�R�O�I�N�i�k���q�R�j
�}�j�@�T�O�Q�P�V�R�~�n�i��q�P�j
�}�j�@�T�O�Q�Q�P�T�n�R
�X�n�t�S�Q�@�T�P�O�N�V
�X�n�@�S�T�@�@�S�T�N�V
�X�n�t�S�S�@�@�P�W�N�V
�P�X�W�S�D�P�P�D�O�T�r�c�ɂ�
|
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��16��(��)22��58��54�b
|
|
�^�C�g��
|
�J��̖��������u�B���O���v
|
|
|
��B�̊F�l���A����v���܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł���܂��B
�}���l��38�l
���k�C���̊ȈՋO�����F�X�Ȑ��������^���̖�ڂ������ł��傤
�@�吳�����A���������ȏ��ǂ́u�k�C�����v���A
�������̊J�������y�ъJ�ւ̕����A����i�Ƃ��āA
�u�B���O���v�̕~�v�悪���Ă���܂����B
�����āA�P�X�Q�T(�吳�P�S)�N�����������E���W�Â̊J�ʂ���A
���S���̉w��������ւƘH�����݂��s��ꂽ�̂ł���܂��B
���́A�����Ȃ���_�яȂւƏ��ǂ��ς��A
�u�ȈՋO���v�ւƖ��̂����߂��ē��͉�����w���i����܂��B
�@�}���l��38�l�̌�L�q�̂Ƃ���A
�S�������\�ɉ̓o�A�l���A�ʊC���̒��c�O�����f�ڂ����Ɏ���A
�S���̓S���t�@���ɂ����݂��F�m�����悤�ɂȂ�܂����B
���H�������̂��߁A���a�S�V�N�Ɂu�l�����c�O���v���p�~����A
�k�C�����L�̊ȈՋO���͎p�������Ă���܂��B
�@�������A�S�����ɂ́u�c�k�v��u�c�b�v����������铙�A
�n��̑��Ƃ��Ă̖������m������Ă����悤�ł��B
(�Q�l�����u�V���ЕҁE���{�S���n�}���P���v���)
�@�����ɂ́A�c���ꂽ��������l�@���邵���Ȃ��̂ł����A
���������R�ɑË������������J�ɂƂ��ẮA
�ȈՋO���̓���͂܂������u��]�̌��v�������̂ł��傤�E�E�E�B
���u���ԕ��v�͑��������̒��Âł��傤
�@�ڍׂ͂킩��܂��A�����Ȃ̂ł����E�E(���)�B
��サ�炭�A�u�ےJ�v����́u��d���v�������Ƃ����b��
���������Ƃ�����̂ł����E�E�B
�����Ŋ����u�c�b�v�Ȃ̂ł��ˁB
�����̐����d�Ԃ̑z���o�́A�u�����������v���J�ʂ����ہA
�u�S�v�e���ƒr�ܔ��̏��}�u���������v�s�Łu����詓��v��ʂ������Ƃł��傤���B
�����A���S�ł̍Œ�詓�������(?)�ƋL�����Ă���̂ł����E�E�B
��B�̊F�l���ɕ⑫������K���ł���܂��B
�@���X�Ǝ��炵�܂����B�܂��A���e�v���܂��B
�ȏ�A�u�����v�ƕ����ĉߏ蔽�����Ă��܂���
�u�������c�����c�v�́u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
|
���e��
|
�G��
|
|
���e��
|
2008�N11��17��(��)15��08��22�b
|
|
�^�C�g��
|
�ȈՋO��
|
|
|
���d�c76 109�l�F
>
�����u�V�����v�̍��Z�ɂ��Ζ������o��������A
�����A���z���̍������B�e�Ɖ]���A������
����Ɖ]���u�S���v�͗ǍD�ł��ˁi^^�j
�����Ƃ��A�����炪���C���ꂽ�����͊��ɁA�������͔p�~����Ă������Ɣq�@���܂��B
���V���w�ɂ��������@�{20�n�q�Ԃ��A�z�e���c�Ƃ��I�����ċv�����l�ł����A�����
�����z�e���́A������̏����_����c���݂̂������ł��ˁB
>
�S�C�������k�̕ی�҂̕����A���Z���������܂Ɂi�����j�ʊw�Ɏg�����̌�
����͋M�d�Ȍ�b���f���܂����ˁB�ȑO�A���k����Ƃ̎G�k�ŁA�b�肪�o�g�n�ɋy�сA
������p�~���ꂽ�������Œʊw���Ă��Ȃ��������A�Ɛ�o�������A�b������オ��A
���ꂪ�߂��āA�K�莞�ԓ��Ɋ̐S�̏��k���Z�܂�Ȃ������A�Ƃ������s�k������܂��B
����͂���Ƃ��āi^^�j�o�g�n�Ȃǂ̑F���́A���Ƃ��ė��������ꍇ������܂����A
�n���n�u�S�v�ɂƂ��ẮA�L���ȁu�c�ƌ���v�ł͂Ȃ����Ɗ�����G���ł����i^^�j
>
�n��̑��Ƃ��Ă̖������m������Ă����悤�ł��B
���쌧�ؑ]�ɏے������X�ѓS���̍Ő����Ɠ��l�A�����K�̘͂H���Ԃ�L���������
���Ȃ��炸���݂����l�ł��ˁB�X�ѓS���̏ꍇ�A�X���̒Ìy�⍂�m���̋������ł́A
�[�w���������̘H�����A�R�ԕ��ŕ�������z���q���鎖�������i�Ìy�̏ꍇ�́A
�Ìy�����ƒÌy�S���A�o���̉����������ł����ƋL�����܂��j�ȈՋO���ł��ޗႪ
���������̂Ƒz�����܂��B
���E���c�O���̕��z������ƁA�Ύ듖�ʂŎD�����ɐڑ��������ʒ��c�������A������
���k�ɕC���ł��ˁB�����͕l�����c�A���k�͉̓o���c�i�����͈��N�A�}�K����
�������܂����j���L���ł��ˁB
�ȑO�ɂ����y�����L��������܂����A�w������A�D�y���t���̈ړ��ɁA���Q�p�n�l��
������14�n�u�V�k�v�𗘗p�����ہA�̓o���c�O�����ڑ��������ڕʉw�ł́A�L������
�R�����ׁA�Ґ��̑����������z�[���Ɏ��܂�炸�i���̌�A���B�����l�ڕʂ̊X���A
��s�s�Ɍ��������Ɂj���Ղȉw�̎��ӂ̕��i�����܂��āA����ł��}�s����܂�Ƃ́A
�ȈՋO���ڑ��̗��j���ɒB�ł͂Ȃ��ƁA���S�����L��������܂��B
>�u�ےJ�v����́u��d���v�������Ƃ����b�������Ƃ�����̂ł���
�����u���A�A���v�܂Ŏ�|�����u�_�ƓS���v���O�g�ł�����A���݂̐w�e���炷���
���X����������ł͂���܂��ˁi^^�j
|
��y������(471)�@����20�N11��17���`11��19��
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��17��(��)22��07��52�b
|
|
�^�C�g��
|
�돟���͂��炵�����]�ł�!!
|
|
|
�A�����Ă���܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł������܂��B
�G���l
�����z���̍������B�e�Ɖ]���A�����Տ���Ɖ]���u�S���v�͗ǍD�ł���
�@�܂������A���̂Ƃ���ł����B�l�G���ꂼ��̎���ɂ���܂������A
���ɐS�Ɏc��̂́A����ŏI�́u�Ƃ����v��
�u�V�돟詓��v����u�V���v�ɉ����Ă��钬�̖�i�ł��B
���E�ɓW�J����u���̓���v�߂Ȃ���A
��������ɏƂ炳��Č��z������ԑ��͂܂��Ɂu�V����i�v�ł����B
�����E���c�O���̕��z������ƁA�`�����⓹�k�ɕC���ł��ˁB
�@�����̋Ζ��Z�ɁA�u���W�Áv����]���Ă�������������܂��B
�Ƃɂ����A�u����v�Ɓu�����v�����Ȃ��A
�Ƃ��q���n���u�Ăāu�Q�q�v����Ă��Ă��A�S���u��a���͂Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB
�����⓹�k�͂��̂悤�ȏ��������A�u�ȈՋO���v�̖��������߂ė����ł��܂��B
�u�ƒn�����Nj��H�܂ł͎ԂłP���Ԃ�����B�v�ƌ��̓������b�������Ƃ�����܂��B
�������A�u���W�Áv����u���H�v�܂ł�
�u�P�O�O�q�v�͂���͂��Ȃ̂ł����E�E�E(?!)�B
�@�܂��A���e�v���܂��B
�ȏ�A�}�s�z�O�l�̎ʐ^�ɑz���o���S��u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
|
���e��
|
�}���l��38
|
|
���e��
|
2008�N11��18��(��)11��01��10�b
|
|
�^�C�g��
|
�k�C����B�S��
|
|
|
ED76109�搶
�u�S���s�N�ƃ��A���A���S�ԗ�����1960�N12���Վ������v�ɏo�Ă��܂��ˁB
���ԕ���DC����������̃L�n111-112�ł��傤�B�i���v�S���L�z�n�j54-55���S����
�L�n�j40603-40604��40704-40705��111-112����S111-112�j���a5�N11�����{���q
�{�X���72���i��32�j�A���d13.2���ALWH=11720����2640��3455�����A�G���W����
Workeshire�F6SRL��Hino�@DS40�@150HP/2400�������B
����PC�i�n501�A�z�n502�ASL��8620�n��8621�C8622�A�X�P�l�N��5704�A
DL���[�^���[DR202CL�A�P�Ԃ̃K�\�����J�[�L�n101-102�A���b�Z���̃L2------
���̓S����m�y�܂Ŕ����Ă����̂ł��ˁB
�L�n22�^�C�v�ő�Ԃ�TR26��TR29�݂�����DC����ɓ����������ł���----
�n�}�ł́u�����v����X�ыO����������Ă��܂��B
�r���Ɂu�����v�i���d���̃}�[�N�H�j������܂��B
�u�͐��S���v�̗��̌���������o�Ă��܂��B
|
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��18��(��)18��40��41�b
|
|
�^�C�g��
|
Re.�k�C����B�S��
|
|
|
���炵�܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł������܂��B
�}���l��38�l�y�юG���l
�u�k�C����B�S���v�́A�P�X�Q�S(�吳�P�R)�N��
�\���x���́u�V�����v����H�����J�n����A
�u��m�y�v���o�R���ē����́u����v�܂ł̕~�v�悪���Ă���܂����B
�������A�u�Ζk�{���v�̊J�ʂɂ���āu��m�y�v�܂łōH�������f����A
�u�V���E��m�y�v�ł̉^�s�ɂȂ�܂����B
���̌�A�P�X�U�W(���a�S�R)�N�ɋ���(��������)�E�Z���Ԃ́u�F��詓��v��
�D�y���^�ǂ���̍s���w���̌��ʁA
�g�p�s�ƂȂ��Ă��܂��A���N�P�O���ɑS���p�~�ƂȂ��Ă���܂��B
�@�}���l��38�l�̌�w�E�̐w�e�ɉ����A
�u�����v�u�g���v���̉ݎԂ���T�O���قǕۗL����ȂǁA
�\���k�����̋M�d�ȓS�H�Ƃ��Ċ��Ă���܂����B
���n�}�ł́u�����v����X�ыO����������Ă��܂��B
���r���Ɂu�����v�i���d���̃}�[�N�H�j��
�@���̒n��́u�g�����E�V�v�ƌĂ�Ă���A
���̎R���݂ɉ����āu�����v��u�G�]�}�c�v�̌����т��L�����Ă��܂��B
�����́u�V���c�я��v�����ǂ���n��ŁA���ދƂ�����Ȓn��ł���܂����B
�@�܂��A��O�u�\����_���v�̌��݂ɍۂ��ẮA
���ݍ�ƈ����̗��p�Łu�k�C����B�S���v�͂��Ȃ�̐�����悵��������
�������b���Ă���܂��B
�܂��A���e�v���܂��B
�ȏ�A��������́u���g�v�̓����ɔw��������u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
��y������(472)�@����20�N11��19���`11��24��
|
���e��
|
�G��
|
|
���e��
|
2008�N11��19��(��)08��16��10�b
|
|
�^�C�g��
|
�ȈՋO��
|
|
|
���d�c76 109�l�F
>
����ŏI�́u�Ƃ����v�Łu�V�돟詓��v����u�V���v�ɉ����Ă��钬�̖�i
�V���̓��ΌQ���ǂ�قǂ̋K�͂��͔���܂��A�m���������Ղ���P��������
��i�̔@���nji��A�z���܂��B�����ł��ƁA������p�����u�k�l���v���A����E�G��
�������生�ٕ���ɉ���r���ʼn��]���ꂽ���ΌQ���A�Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��ˁB
>�u����v�Ɓu�����v�����Ȃ��A�Ƃ��q���n���u�Ăāu2�q�v����Ă��Ă��A
���ɁA�W�Ð��̎ԑ����i���̂��̂ł��ˁB�Ȃ��A�䂪�n���ɂ��A�Ƃ�
1�`2km
����A
�������͂��̂����O�Ƃ����R�ԕ��̏o�g�䂦�A�X���ɉ��h���Ă��������������܂����B
1970�N��܂ł́A��d���̐��т��͂��Ȃ���c���Ă��܂����˂��B
>
�����⓹�k�͂��̂悤�ȏ��������u�ȈՋO���v�̖��������߂ė����ł��܂��B
�O���~�݂̍����@�߂��u�n���S���v��u�O���@�v�ł͂Ȃ��u���H�̑�ցv�ł�����ˁB
����ɂ��Ă��A���z�̍������l����Γ��H�̕����Z�ʂ��������Ǝv���܂����A������
���n�Ȃ����D�Y�n�ł́A�O���̕����~�݂��e�Ղ������̂ł��傤���B
>�u�ƒn�����Nj��H�܂ł͎ԂłP���Ԃ�����B�v�ƌ��̓������b�������Ƃ�����܂��B
��w����A�����^�E�J�[�ŁA�O�������ē�������������o������\���A���̊��o��
�����o���܂����A�Ƌ��ē����������́A�䎌�̂݁u�T�[�L�b�g�̘T�v������
���邢�́u�}�b�h�E�}�b�N�X�v�������ɋ�����̂����X�ł����i^^�j
����ȃh���C�u�̍Œ��A�W���̊X��ʉߒ��A�O���炵������u������A���ɗ[���ŁA
���h��̓����������C�ɂȂ����̂ŁA���̂܂ܒʉ߂��Ă��܂��܂����B�����ɂȂ��āA
�ܑ̖������������Ɖ���܂�܂��B
|
|
���e��
|
�z�G�V�O�R�O
|
|
���e��
|
2008�N11��22��(�y)11��45��55�b
|
|
�^�C�g��
|
����̏���ɂ�
|
|
|
�@������r�k�u�[���̂���A
�ǂ��炩�ƌ����Ǝԗ����̂̎ʐ^���d�_�ɎB���Ă��������A
�b�U�Q�̏d�A�Ȃǖk�C���̏��@��Ԃ��B�肽���Փ��ɋ���A
���x�������K��܂����B
�@�u����v�ƌ����w���́A�r�S�Q�N�ɕ������ꂽ�m�g�j�̂s�u�h���}�u���H�v�̒��ŁA
����o���ł����A�@�֏���i���K���H�j�̉��{�Ǖ��i�R�c���j��
��l���̎����Y��Y�i�������j�̖���}�i���R���q�j���A
�엎�����邽�߂ɐ�Ɉ�l�Ŋ�����ʂɍs����}�ɑ��āA
�Ǖ����u�������A����ō~�����v�ƔO�������Ă���V�[������ۂɎc���Ă��āA
�\�Ă���s���Č������Ǝv���Ă����ꏊ�ł����B
�@����`��m���ԂŁu�j�Z�R�v��c�T�P�̋q�ԗ�ԁA
������̓�ڂX�U�̉ݕ��Ȃǂ��B��܂������A
�w�ł������B��܂����B�摜�͂��̓��̂P���ł��B
���̉���̏o���M���@����ۓI�ł����B
�@�@�P�Q�P���@���ف�����@�@�c�T�P�R�U�V�i�݁j�@�r�S�U�D�S�D�P�P�@�@����
|
|
���e��
|
�}���l��38
|
|
���e��
|
2008�N11��23��(��)17��57��10�b
|
|
�^�C�g��
|
�ȈՋO��
|
|
|
ED76109�l
�̋g�앶�v���ҏW�́u�ʐ^�Ō�����30�N�̓S���ԗ��v72�łɁu�l�����c��DC]�C
�u�y�����c�n2�q�ԁv�A�u�ߋ����c��L�^DL?GL?]���o�Ă��܂��B
����ɏ��a32�N�̍��Ɂu���A�̔n�ԋO���v�����O����̋M�d�Ȉꖇ�ł��B
|
��y������(473)�@����20�N11��24���`11��27��
|
���e��
|
ED�V�U�P�O�X
|
|
���e��
|
2008�N11��24��(��)11��37��48�b
|
|
�^�C�g��
|
�u�S�v�Ȃ��y����
|
|
|
�@�������������܂��B�u�d�c�V�U�P�O�X�v�ł������܂��B
�@�}���l��38�l
�@�u�ȈՋO���v�ɌW��l�X�Ȏ������̌�掦�ɂ��āA�S���炨��\���グ�܂��B
�����ɂ́A�u���{�S�����s�n�}���ꍆ�@�k�C��(�V���Е�)�v�L�ڂ�
�K�\�����@�֎Ԃ��q�ԁE�ݎԂ��������Ă���
�u�y�����c�O���v�Ɣn���ؑ��q�Ԃ��������Ă���
�u�̓o���c�y�����v�̎ʐ^���x�����茳�ɂȂ��ł��B
�����̎��Ƃɂ���u�L�c���h���v�̓S���ʐ^�W(���a�S�T�N����̂���?)��
�m���u�ʊC���c�O���v�̎ʐ^�������̂��A
�u�ȈՋO���Ƃ̏o��v�ł������悤�ɋL�����Ă��܂��B
�������A�}���l��38�l�̂��b�ŋ������o�Ă��܂����B
�d���ɗ]�T���ł���A�ߗׂ́u�����}���فv���Ă��Ă݂����Ȃ�܂����E�E�E�B
�@�z�G�V�O�R�O�l
�@���߂܂��āB�u�d�c�V�U�P�O�X�v�Ɛ\���܂��B
�����̎Y�Ȃ̂ł����A���݁u�k�̑�n�v�ɍ݂��Ă���܂��B
���������u���q�v�̎ʐ^�ɁA�����̑z���o���S��܂��B
�u����v�́u�P�Q�P���v�E�E�E�B�u�R���v�̋��q���p�������āA���Q�Q�N�ł��ˁB
������x�A���̏��w�u��ږ��v�ɍ~�藧���Ă݂����Ȃ�܂����E�E�E�B
�@�Ō�Ɂu�Y���v�Ȃ̂ł����E�E�B
����A�ٖ��Ə��p�Łu�D�����v�ɏ��܂����B
���܂�������ԗ����u���b�h�g���C���v�̉����ԁB
���������A���a�S�R�N���u���q�v����������
�u�c�b�v������܂���ł����ł��傤���B
�m���u�L�n�O�v�Ə̂��Ă����悤�ȋL��������̂ł����B
��B�̊F�l���ŁA�䋳��������������K���ł���܂��B
�@���X�Ǝ��炵�܂����B�܂��A���e�v���܂��B�ȏ�A�u���N�q�ԓS�����v�ł����B
|
|
|
�@
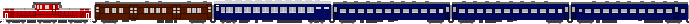 |
|
|
|

